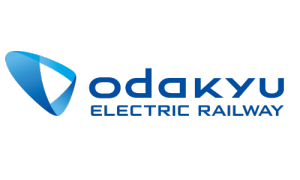大企業向け ノーコード(SmartDB) vs ローコード(外資系)
ノーコードとローコードは、名前こそ似ていますが、その本質には決定的な違いがあります。
ローコードは、あくまでITプロフェッショナルを対象とした開発支援ツールであり、プログラミング知識や技術スキルが前提となります。
一方ノーコードは、非エンジニア=市民開発者でも業務アプリを構築・改善できる自走型ツールであり、業務部門が主体となるDX内製化を可能にします。
中でもスマデビ(SmartDB)は、2004年の企画段階から完全ノーコード=プログラムレス設計を貫く、現場と情シスの協創を実現するプラットフォームです。
その設計思想と成熟度は、他のツールとは一線を画します。
【 比較表 】
※スクロールできます
| ノーコード(SmartDB) | ローコード(外資系) | |
|---|---|---|
| 開発主体とスキル要求 | 非エンジニアを含む現場部門が自ら業務アプリを構築可能。直感的UIとテンプレートで即運用開始でき、IT部門はガイド役に集中可能。 | ITエンジニア主体での開発が前提。現場部門が直接構築することは困難で、要件定義後もIT部門依存が強い。 |
| スピードと柔軟性 | ノーコードで短期間にプロトタイプ→改善を回せる。要件変更や追加も即時反映でき、現場の変化に迅速対応。 | 開発にコード記述が必要なため変更対応に時間とコストがかかる。アジャイル運用が制限されやすい。 |
| 導入・展開コスト | 初期構築・機能追加が短期間かつ低コスト。スモールスタートから全社展開まで投資効率が高い。 | 開発・カスタマイズの工数が多く、初期費用・保守費用ともに高止まりしやすい。 |
| 運用負荷と保守 | 現場で設定変更や機能追加が可能。軽微な修正は自己完結し、IT部門の負担を削減。 | コード変更やテストが必須で、小規模修正でもIT部門の対応が必要。保守工数が高止まりする。 |
| 変化対応力 (経営環境変動への即応性) |
現場主導で制度改正・市場変化・組織改編などに短期間で対応可能。経営判断から現場反映までのリードタイムが短い。 | 環境変化への対応には開発・テスト工程が必須で、リードタイムが長くなりがち。 |
| 日本企業との親和性 | 日本独自の業務フローや承認プロセスに標準機能で対応。追加開発は最小限で導入後すぐ適用可能。 | 外資系設計思想のため、日本特有の業務慣習に合わせるには大幅なカスタマイズと開発工数が必要。 |
| グローバル対応と ローカル最適 |
国際時差、多言語対応に関する基本機能が2004年の設計段階から盛り込まれ、海外拠点展開の先行実績も豊富。 | グローバル基準設計が中心で、ローカル最適化には追加開発が必要。国内業務への即応性は低い。 |
| 開発・運用の体制 | 現場部門とIT部門が協働。現場は業務ロジックを主導的に決定または直接構築し、IT部門は全社インフラやセキュリティ、システム連携を統括。ウォーターフォール型の制約から解放され、アジャイル的な継続改善を促進。 | 情報システム部門と外部ベンダーの組み合わせが主流。ベンダー調整や契約管理が不可欠でウォーターフォール型開発。構造的にコスト増となりやすく、開発・改善・運用の柔軟性も制約されやすい。 |
| 戦略的効果 | DX内製化を加速し、現場の自律的改善文化を醸成。導入効果が広範囲に波及し、全社的な変革を推進。 | 部門単位での効果はあるが、全社的な内製化・文化変革にはつながりにくい。IT部門依存が温存される。 |