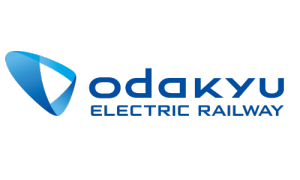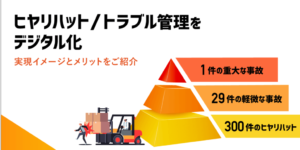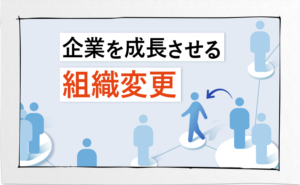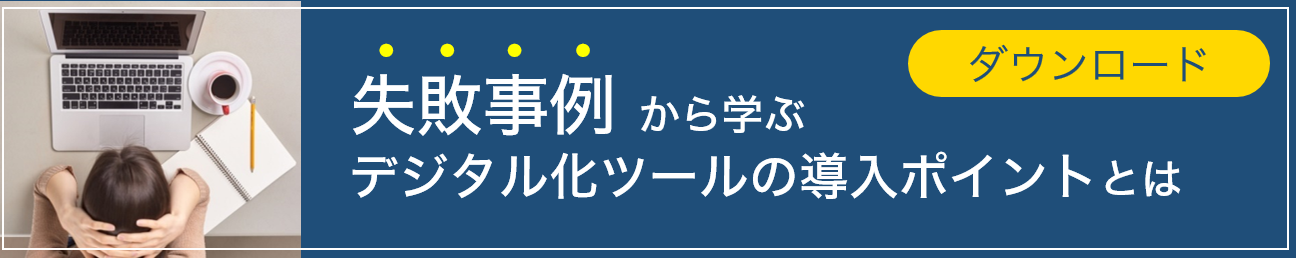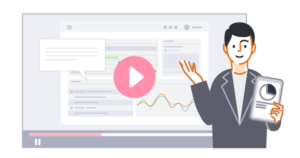近年のソフトウェア開発の現場では、深刻なIT人材の不足に加え、対応すべきテクノロジーや業務領域の拡大が進んでいます。その結果、開発者一人ひとりに求められる負荷は年々増し、限られたリソースのなかで多くの課題に対応しなければならない状況が続いています。
こうした課題を背景に注目されているのが、開発者が本来の開発業務に集中できる環境を整える「プラットフォームエンジニアリング」というアプローチです。共通基盤を整備し安全かつ効率的な開発体験を提供することで、生産性の向上や属人化の解消が期待されます。
本記事ではプラットフォームエンジニアリングの基本概念から具体的な導入メリット・実践的な進め方まで、開発現場の課題解決に必要な情報を体系的に解説します。現在の開発体制に課題を感じている方、開発チームの生産性向上や運用負荷の軽減を検討している方はぜひ最後までお読みください。
目次 [閉じる]
プラットフォームエンジニアリングとは?
プラットフォームエンジニアリングとは、開発者が効率的にアプリケーションを構築・デプロイ・運用できるよう、セルフサービス型の内部開発プラットフォームを設計・構築・維持する手法です。
昨今、クラウド活用の進展やマイクロサービスの普及・セキュリティ対策の重要性の高まりにより、開発現場の複雑化は増しています。プラットフォームエンジニアリングは、こうした複雑さを共通基盤の整備によって吸収し開発者の負担を軽減するアプローチとして注目されています。
調査会社ガートナー社のパンカジ・プラサド氏は、「ソフトウェアのインフラを開発者自身が運用すべきとする考え方が、大規模かつ分散的なアプリケーション開発に混乱をもたらしている」と指摘しています。
こうした課題に対しプラットフォームエンジニアリングは、共通のツールやインフラを使いやすく提供することで、特に大規模かつ複雑なシステムを運用する金融機関や大企業で開発の自律性と安全性を両立するアプローチとして期待を集めています。
プラットフォームエンジニアリングの目的
プラットフォームエンジニアリングの目的は、開発チームがより早く・安全に・効率よくソフトウェアを開発・運用できるようにすることです。具体的には、以下のような作業を標準化・自動化することで開発者の負荷を軽減します。
- 開発環境の構築と管理
- CI/CDパイプラインの設定
- インフラのプロビジョニング
- セキュリティポリシーの適用
- 監視・ログ管理の設定
プラットフォームエンジニアリングを導入することで、新しいサービスのリリースをする際に必要な環境構築やセキュリティ設定などの作業があらかじめ整備された仕組みで自動化・標準化されます。開発者は周辺作業に時間を取られることなく、本来の業務である開発や設計に集中することが可能です。その結果、リリースまでのスピードを大幅に向上させられるようになります。
結果として市場の変化に素早く対応しユーザーニーズに応える製品を短期間で提供できるため、企業の競争力向上に貢献します。
DevOpsとの違い
DevOpsとは、ソフトウェア開発(Development)と運用(Operations)の連携を深め、開発からリリース・運用までの一連の流れを効率化・自動化する考え方です。開発チームと運用チームが協力しスピーディーで安定したサービス提供を実現します。
インフラの自動化や継続的インテグレーション/デリバリー(CI/CD)、監視体制の整備などはDevOpsの具体的な手法です。
一方、プラットフォームエンジニアリングは、DevOpsの取り組みを誰でも簡単に活用できる「共通の土台(プラットフォーム)」を構築・提供する役割を担います。
Googleは、両者の関係について以下のように述べています(※)。
“プラットフォーム エンジニアリングは「単に DevOps を発展させたもの」ではありません。そうではなくこれは「DevOpsをシフトダウン」してプラットフォームに組み込む試みであり、デベロッパーに高い専門性を要求することなくDevOpsのプラクティスを実践できるようにするものです。”
つまり、DevOpsの技術的な実装や複雑な運用を共通基盤に落とし込み誰でも使える形にするのが目的です。
たとえばボタンひとつでデプロイできる仕組みや標準化されたセキュリティ設定を用意できれば、開発者は簡単にDevOpsのベストプラクティスを活用できます。プラットフォームエンジニアリングは高いDevOpsスキルを全員に求めるのではなく、安全かつ効率的に開発・運用ができるようにする「裏方の仕組みづくり」の役割を果たします。
※出典:Google|プラットフォーム エンジニアリングに関する5つの誤解:プラットフォーム エンジニアリングとは一体なのか
SREとの違い
SRE(Site Reliability Engineering)もプラットフォームエンジニアリングと混同されやすい言葉のひとつですが、その目的と対象ユーザーに明確な違いがあります。
SREは、サービスの信頼性を維持しつつ効率的に運用することを目的としたアプローチです。主に外部向けのプロダクトやサービスを対象としています。SLO(Service Level Objective)をベースに、パフォーマンスの最適化やインシデント対応・稼働率の維持などに取り組みます。モニタリング体制の整備、アラートの最適化、自動復旧の仕組み構築などが具体的な活動例です。
SREは、主に外部向けサービスの可用性や信頼性の向上を目的としたアプローチです。SLO(Service Level Objective)をベースに、パフォーマンスの最適化やインシデント対応、稼働率の維持などに取り組みます。たとえばモニタリング体制の整備やアラートの最適化、自動復旧の仕組み構築などがその具体例です。
一方でプラットフォームエンジニアリングは、社内の開発者が効率よく開発・運用できるようになることを目的としたアプローチです。開発チーム全体が使いやすい共通基盤を整えることで、開発者の作業環境全体の最適化を実現します。
つまりSREは「サービスの信頼性(外部ユーザー体験の最適化)」に、プラットフォームエンジニアリングは「開発効率(社内開発者体験の最適化)」に焦点を当てています。いずれも現場の最適化を目指す取り組みであることは同じですが、目的や視点に違いがあります。
プラットフォームエンジニアリングが注目されている背景

続いて、プラットフォームエンジニアリングが注目されている背景を以下5つの視点から解説します。
- IT人材・リソース不足が深刻化している
- 開発者の認知負荷が増加している
- DevOps・SREが限界を迎えている
- 迅速な開発体制が求められている
- 大規模開発をする場合「共通基盤」が求められている
IT人材・リソース不足が深刻化している
経済産業省の調査によると、2030年に最大約79万人のIT人材が不足すると予想されています。すでに高度なスキルを持つIT人材の確保が困難になっており、企業は限られた人数で多くの業務をこなさなければならない状況に直面しています。情報システム部門においても、既存システムの保守・運用業務で手がいっぱいになり新たなデジタル施策に十分なリソースを割けないケースが増加しています。このような状況下で、プラットフォームエンジニアリングによる基盤整備と自動化の推進は、限られた人的リソースを最適化し業務効率を大幅に向上させる有効な手段として注目されています。
出典:経済産業省(商務情報政策局)|参考情報(IT人材育成の状況等について)
開発者の認知負荷が増加している
開発者の認知負荷が増加していることも、プラットフォームエンジニアリングが注目される理由のひとつです。
企業が提供するサービスは年々高度化・複雑化しており、それに伴って開発者に求められる技術領域も広がっています。さらに、クラウドの普及や人材不足の背景により、従来はインフラチームや運用チームが担っていた作業を開発者自身が対応する場面が増加しています。
たとえば、AWS・Azure・GCPなどのクラウド環境構築やDocker・Kubernetesによるコンテナ管理、CI/CDパイプラインの設定、セキュリティポリシーの適用、監視システムの構築などが開発者の責任範囲に含まれるようになりました。
これらの多岐にわたるタスクは単に時間的な負担になるだけではありません。本来の業務とは異なる領域にまで注意を向ける必要がある点で、開発者の認知負荷を大きく増加させます。その結果、設計やコーディングといった本来の業務に集中する時間が減り開発スピードや品質の低下を招くおそれもあります。
プラットフォームエンジニアリングは、このような認知負荷を軽減し、開発者が本来の価値創出に集中できる環境を整えるうえで、重要な役割を果たします。
DevOps・SREの取り組みを支える基盤が必要になっている
DevOpsやSREは、開発と運用の連携を深め、ソフトウェアのリリースを迅速かつ安定的に進めるためのアプローチや考え方です。しかし、これらの取り組みを現場で実践するには開発者が環境構築や運用にも柔軟に対応できることが求められ、その負担が課題となることがあります。
プラットフォームエンジニアリングは、DevOpsやSREのベストプラクティスを共通の基盤に組み込み開発者が高度な専門知識を持たずとも、それらを活用できる環境を提供するアプローチです。これにより、DevOps・SREの取り組みを組織全体でより効果的に推進できるようになります。
迅速な開発体制が求められている
ビジネスや社会のスピードが加速するなかで開発納期は年々短縮する傾向にあります。新サービスやアプリの市場投入までの競争が企業間で激化し、短期間で新機能をリリースすることが求められるようになりました。
こうした変化のなかでは企業のユーザーニーズに応えるスピードが競争力を左右します。短期間で高品質なサービスを届けることが重要となり、開発効率を高める手段としてプラットフォームエンジニアリングの重要性が高まっています。
プラットフォームエンジニアリングにより、アイデアの発案から実装、市場投入までのリードタイムを大幅に短縮し競争優位性を確保できます。
大規模開発をする場合「共通基盤」が求められている
大規模な開発プロジェクトでは、多くの開発者やチームが関わります。各チームや個人が独自のツールや手順で作業すると、運用のバラつきが生じ非効率になるだけでなく、以下のようなトラブルの原因にもなります。
- 環境の差異によるバグの発生
- デプロイ手順の標準化不足による障害リスク
- 技術負債の蓄積とメンテナンス性の悪化
- 新メンバーのオンボーディング期間の長期化
プラットフォームエンジニアリングによる共通基盤の整備は、これらの課題を根本的に解決し大規模開発においても一貫した品質と効率性を確保できる環境を提供します。
プラットフォームエンジニアリングの進め方の例
プラットフォームエンジニアリングを成功させるためには、技術的な実装だけでなく組織的な取り組みも重要です。開発者や関係者の声を継続的に反映し、全社での活用を促進する体制づくりが求められます。
ここでは、プラットフォームエンジニアリングの進め方の例を5つ紹介します。
- 課題・目的の設定
- 要件の収集・改善計画
- ツール選定と導入支援
- インターフェースの整備
- 社内への浸透
課題・目的の設定
プラットフォームエンジニアリングの導入で最も重要なのは、「何のためにやるのか」を関係者全員が理解をすることです。そのために課題・目的を手順にしたがって設定する必要があります。まずは現場の課題を具体的に洗い出し、関係者間で共通認識を持つことがプラットフォームエンジニアリングの第一歩です。 開発者へのインタビューやアンケート調査を通じて、実際に困っている作業や時間のかかっているプロセスを具体的に把握します。たとえば「人手不足で新しいマイクロサービスの立ち上げに3週間かかっている」「環境設定で毎回トラブルが発生する」「デプロイ作業が属人化している」など具体的な課題を収集します。
こうして抽出された課題をカテゴリごとに整理し、どの問題を優先的に解決すべきか、何をもって成功とするか(成功指標/KPI)を明確に定義します。これにより、プロジェクトの方向性を関係者間で一致させることが可能です。導入後の評価基準を共通認識として持つこともできます。
要件の収集・改善計画
次に、要件を収集し改善計画を立てましょう。必要に応じて開発者や情報システム部門、プロダクトマネージャーなど各関係者に調査をおこないます。
インタビュー、アンケート、ハッカソンといった手法でニーズを把握し、優先度を整理したうえでロードマップに反映します。
現場に即したツール選定
ツールは導入することが目的ではなく、現場で継続的に活用されてこそ価値を発揮します。そのため、ツール選定においては流行や機能の豊富さだけでなく現場の課題や開発者にとっての使いやすさを最優先に考えることが重要です。
たとえば、デプロイ作業の属人化が課題であればCI/CDツール、環境構築に毎回時間がかかっているのであればInfrastructure as Code(IaC)や自動化スクリプトの導入が有効です。
課題起点でツールを検討することで導入の目的が明確になり、現場に定着しやすくなります。
プラットフォームエンジニアリングが目指す「自律的な開発環境」の実現につなげていきます。
インターフェースの整備
開発者が迷わず使えるよう、直感的に操作できるGUI(Graphical User Interface)やAPI、テンプレートなどを整備します。使いやすいインターフェースが整うことで、開発者の学習コストや作業の無駄を減らせます。
プラットフォーム設計の鍵となるのが、「ゴールデンパス」と呼ばれる考え方です。開発者がよく通る理想的な作業フローをあらかじめ定義しそれをテンプレート化・自動化して提供することで、作業のブレやムダを減らします。
たとえば、新規マイクロサービスの立ち上げに必要なステップをあらかじめ定義し、ボタン一つで環境構築やデプロイが完了するようにしておけば効率的な開発作業を全員が再現できるようになります。
上記のような取り組みにより、品質やセキュリティ、効率性を保ちながら作業できるようになり属人性も排除できます。
社内への浸透
優れた仕組みも活用されなければ効果は限定的です。プラットフォームの意義や使い方を分かりやすく伝え、利用促進に取り組みます。
勉強会・ワークショップの開催、成功事例の共有、ガイドライン策定などを通じてプラットフォームの意義や使い方を分かりやすく伝えていきましょう。現場の支持を得ることで、プラットフォームの価値はさらに高まります。
プラットフォームエンジニアリングを支えるIDP

プラットフォームエンジニアリングの中核的な手段として注目されているのが「IDP(内部開発者向けプラットフォーム)」です。
この章ではIDPとはなにか、その仕組みや利点、構成要素について詳しく解説します。
なお、IDPを用いなくてもプラットフォームエンジニアリングを実践すること自体は可能です。たとえば、テンプレート・GitOps・共通ライブラリ・Terraformモジュール・社内CLIなどを頼る方法があります。
小規模な組織やプロジェクトでは、IDPをフルに構築しないという選択肢もあります。しかし、開発者体験を継続的に向上させ組織全体での再現性・拡張性を高めるならIDPの導入が効果的です。
IDP(内部開発者向けプラットフォーム)とは
IDP(Internal Developer Platform)とは開発者が自律的にアプリケーションの開発・テスト・デプロイをおこなえるように設計された社内専用のプラットフォームです。アプリケーション開発に必要な機能が、ひとつにまとめられているのが特徴です。
たとえば、CI/CDパイプライン・モニタリング・インフラ管理など開発に必要な各種機能を統合・自動化して提供します。IDPにより開発者が煩雑な作業から解放されれば、本来の開発業務に集中できる環境が整うでしょう。
IDPとプラットフォームエンジニアリングの関係
IDPは、プラットフォームエンジニアリングの実現を支える手段のひとつです。DPを活用することでソフトウェア開発の効率化がより一層進みます。
具体的には、ビルドやデプロイ、モニタリング、ログ管理といった開発プロセスに不可欠な要素を一つのプラットフォーム上に統合。開発者は、個別のツールを行き来することなくワンストップで業務を遂行できるようになります。
また、IDPが一貫したワークフローを提供することで、開発プロセス全体の可視性を向上できます。エラーの減少や迅速なフィードバックが可能になり、チーム全体の生産性向上につながるでしょう。
またIDPは高いカスタマイズ性と拡張性を兼ね備えており、各企業の開発体制や業務プロセスに合わせて最適なプラットフォームエンジニアリングの構築が可能です。
IDPの特徴
IDPの特徴は「セルフサービス化」にあります。セルフサービス化とは、開発者が必要なリソースをインフラの専門知識なしで即座に準備、操作できる仕組みを整えることです。
たとえば、テスト環境やDBインスタンス、CI/CDテンプレートなどを、開発者自身の判断で素早く使える状態を実現します。
これにより、従来はインフラチームや運用チームに依頼していた環境準備や設定の待ち時間が大幅に減少します。他部署への連絡や調整にかかる手間の軽減といった副次的な効果も得られるでしょう。結果として、開発スピードの向上が期待できます。
プラットフォームエンジニアリングを導入するメリット
プラットフォームエンジニアリングを導入することは、開発者にもプラットフォーム提供者にもメリットがあります。以下では、それぞれのメリットについて解説します。
1. 開発者にとってのメリット
開発者にとってのメリットは、以下のとおりです。
- 環境構築の負担が軽減される
- 開発スピードが向上する
- 一貫した開発フローによって品質が安定する
環境構築の負担が軽減される
IDやライブラリ設定・CI/CDの準備・インフラの初期構築など、開発を始めるまでの煩雑な作業が軽減されます。開発者はインフラやパイプラインの準備に時間を取られることなく本来注力すべきアプリケーション開発や機能改善に集中できるようになるでしょう。
開発スピードが向上する
セルフサービス化や自動化によって自律的にリリースまで進められる仕組みを実現できます。リリースまでのリードタイムが短くなり、継続的なデリバリーが現場に浸透します。
開発サイクルが速くなることでユーザーの要望に素早く応えられるため、市場での競争力向上も期待できます。
一貫した開発フローによって品質が安定する
プラットフォームエンジニアリングによって標準化された環境が整うことでコードの品質やレビューの基準が統一されます。
どの開発者が作業しても一定のレベルの成果物を得られるようになり、属人性を排除しやすくなります。開発したソフトウェアの品質が安定し、テストや運用の工程でもトラブルが起きにくくなるでしょう。
2. プラットフォーム提供者にとってのメリット
プラットフォーム提供者にとってのメリットは以下のとおりです。
- 横断的な標準化が実現できる
- セキュリティやガバナンスを強化できる
横断的な標準化が実現できる
プラットフォームエンジニアリングにより、組織内の複数チームや部門を横断して共有のフローやツールを活用し、標準化を実現できます。これにより、技術スタックの一貫性が保たれ運用効率が大きく向上し管理の手間も削減されるでしょう。
たとえば、共通のデプロイメントパイプラインやモニタリングシステムを提供することで個別チームごとの管理コストが削減され、リソースの最適化が図れます。また、一度解決した技術的課題を組織全体で共有できるため同じ問題を何度も解決する無駄を省けます。
セキュリティやガバナンスを強化できる
共通基盤を整えることで、セキュリティポリシーやアクセス権限の設定、監査ログなどを集約して一元管理できるようになります。各チームで個別のルールを運用する必要性が低くなり全社的な統制を強化できます。
また、セキュリティアップデートやパッチ適用も一括で管理できるため、脆弱性への対応が迅速化します。外部規制の遵守や監査対応においても標準化されたプラットフォームがあることで証跡の収集や報告書の作成が容易になり、コンプライアンス面でのリスク軽減にもつながるでしょう。
プラットフォームエンジニアリングで押さえるべきポイント
プラットフォームエンジニアリングの成功には開発者中心の設計、継続的な改善、運用面への配慮の3つが重要です。
技術的に優れたプラットフォームであっても、これらのポイントを満たさなければ現場で活用されず、期待した効果を得ることはできません。
開発者のニーズに寄り添った設計か
現場の開発プロセスや業務フローに合わないプラットフォームはどれだけ高機能でも意味がありません。開発者の日常業務に適合しなければ使われないため、成功には彼らの声を設計に反映することが不可欠です。
直感的なインターフェースや自然に使えるワークフロー、実際の課題を解決する機能を備えたプラットフォームこそが、現場で真の価値を生み出します。
現場の開発プロセスや業務フローに合わないプラットフォームは活用されません。 どれだけ高機能でも開発者の日常業務に適合しなければ意味がないため、成功には彼らの声を反映した設計が不可欠です。 直感的なインターフェースや自然に使えるワークフロー、実際の課題を解決する機能を備えたプラットフォームこそが、現場で真の価値を生み出します。
継続的な改善ができるか
プラットフォームは一度作って終わりではなく、技術や業務の変化に応じて開発者の声を反映し、絶えず進化させていく必要があります。
継続的な改善を実現するためには、以下のサイクルを確立することが重要です。
- 利用状況の定量的・定性的なモニタリング
- 開発者からの直接的なフィードバックの収集
- 新たなニーズや課題の分析
- 優先順位付けと改善計画の策定
- 機能の改良や追加の実装
- 改善効果の測定と検証
継続的な改善をすることで、プラットフォームは組織の成長とともに進化し、長期的な価値を提供し続けられます。
運用方法やトラブル発生時の考慮ができているか
プラットフォーム構築時には、障害発生時の対応やパフォーマンス低下への対策を事前に検討することが重要です。
特にIDP(Internal Developer Platform)を構築・運用する場合、トラブル発生時の原因特定や復旧作業が複雑化し対応に時間がかかるリスクがあります。
効果的な対策として以下の取り組みが有効です。
- プラットフォームの設計段階から開発者の視点を取り入れる
- セルフサービス化を徹底して開発者がリソースを簡単に利用できるようにする
- プラットフォームの利用状況を常にモニタリングして改善を繰り返す
- セキュリティ対策を徹底して定期的に脆弱性診断を実施する
- チーム間でプラットフォームの利用方法やルールを共有して標準化を推進する
ノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」という選択肢
前述の通り、プラットフォームエンジニアリングは、開発者が「本来の業務に集中できる環境を整備すること」を目的としています。つまり、開発者がより効率的に価値を生み出せるようにするための取り組みでありそれが本質です。
しかし、現場レベルでの「開発者の働きやすい環境づくり」を考えるともう少し広い視点が求められます。近年では、IT人材の不足によりエンジニアがレガシーシステムの保守や社内業務の効率化といった、本来の開発業務以外にも多くの時間を割かざるを得ない状況が見られます。
さらに、申請業務やベンダー対応といった開発に直接関わらない付帯業務にも未だに非効率なレガシープロセスが多く残っています。こうした状況のままプラットフォームエンジニアリングだけを推進しても、日常業務の無駄が蓄積し結果的に大きな機会損失を招くリスクがあります。
このような共通課題に対応するには、開発者の利便性だけでなく業務部門を含む組織全体の横断的な業務効率化を支える仕組みが求められます。
そこで注目したいのが、ノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」です。
「SmartDB」は現場部門が直接扱えるユーザビリティを備えた、すでに確立された業務基盤を提供します。そのため、プラットフォームエンジニアリングのような複雑な構築や専用チームによる運用が不要です。非エンジニアでも簡単に業務アプリを作成でき開発者の負担を大きく軽減できます。
人材不足が続くなかでも、現場主導で全社的な業務改善をスピーディに進められる点は大きな魅力です。
標準化と自律的な運用を同時に実現できる「SmartDB」は、プラットフォームエンジニアリングに依存しない現場ニーズに即した新たな選択肢として、今後ますます注目されることでしょう。
現場部門主導でアプリを作成、全社基盤として活用
「SmartDB」の最大の特長は、情報システム部門に依存せず、現場部門のメンバー自身が業務アプリを作成できる点にあります。専門的なプログラミング知識がなくても豊富なテンプレートや共通部品を活用しながら、誰でも一定品質のアプリを作成・運用することが可能です。
さらに「SmartDB」は単なる部門利用にとどまらず、全社的な共通プラットフォームとしての運用にも対応します。全社基盤として活用することで、開発者の負荷を最小限に抑えつつ業務改善を組織全体で推進できるようになります。
高いセキュリティ
「SmartDB」は大企業に選ばれる堅牢なセキュリティ体制を備えており、安心・安全に利用可能です。 承認ルートが明確でワークフローやデータの証跡も残せるため、ガバナンス強化にも寄与します。
セキュリティ対策の一例
- アクセス制限
- 不正ログイン対策
- 脆弱性対策
- データ消失対策
- 障害検知・復旧対策
- ヒューマンエラー・内部不正防止
- セキュリティリンク
開発者の負担を軽減したい方や、現場部門主体で業務改善を進めたい方にとって、「SmartDB」は業務プロセス改善の最短ルートとなるでしょう。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

3分でわかる「SmartDB」
大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」でどのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。
詳細・お申し込みはこちら