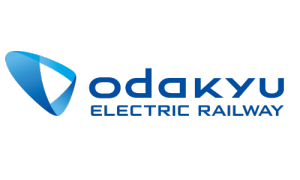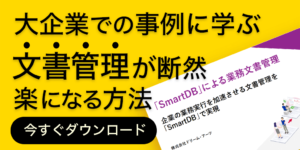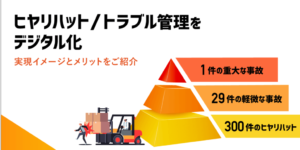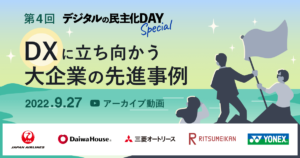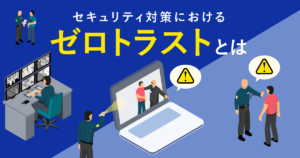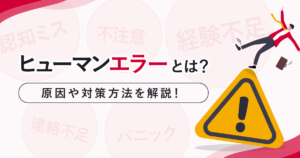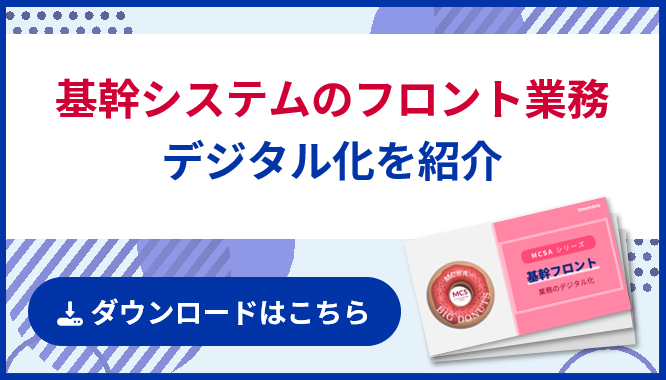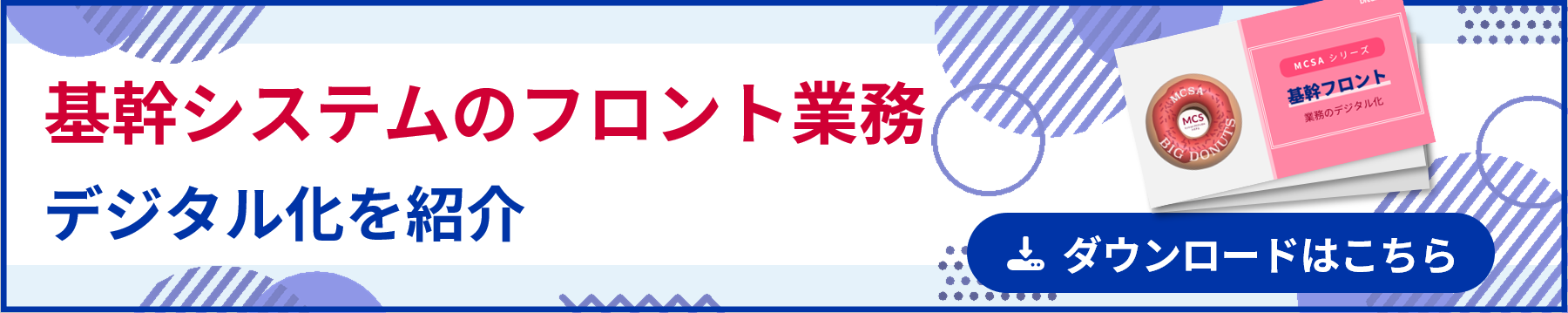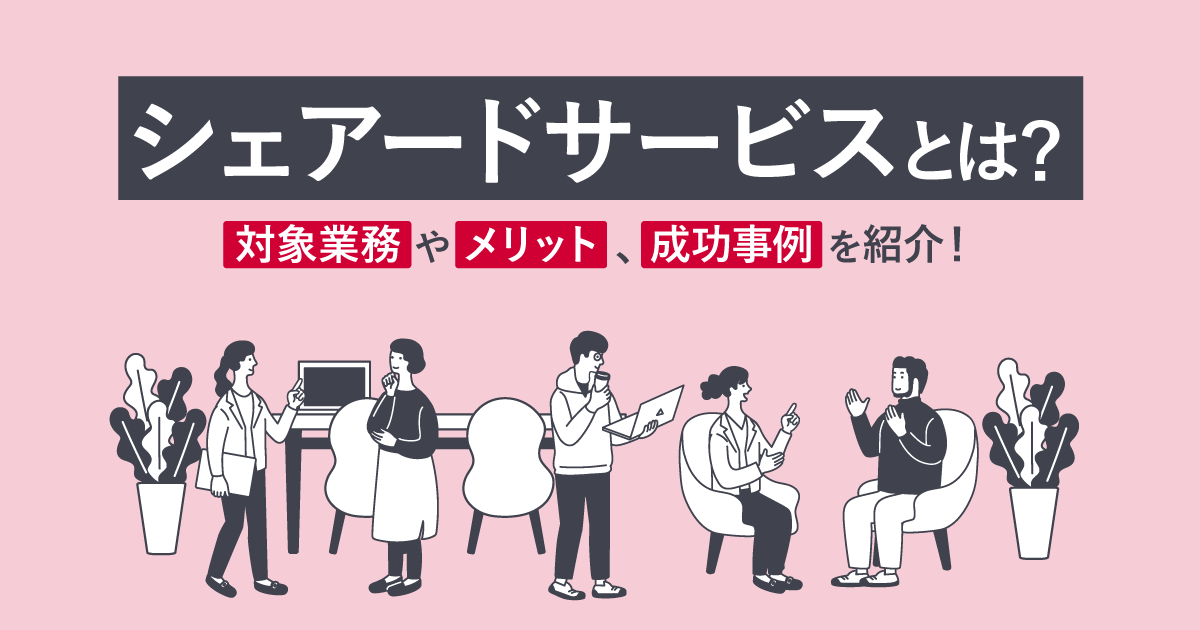
目次 [閉じる]
「シェアードサービスとは?」
「聞いたことはあるけれど、具体的なメリットがわからない」
「成功している企業の事例を知りたい」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。前半はシェアードサービスの概念やメリット・デメリットについて、後半は導入時の流れや事例をご紹介します。
シェアードサービスを検討している方は、ぜひお役立てください。
シェアードサービスとは

シェアードサービスとは、複数企業が属するグループ企業内において、共通しておこなわれる間接業務を一か所に集約する手法です。たとえば、経理や人事、物流、情報システム管理など、企業ごとで内容に差異のない業務を集約し、一元化することで効率化を図ります。
以下では、従来との違いや混同されがちな用語と比較しながら、シェアードサービスの概要について解説します。
シェアードサービスと従来の部門との違い
シェアードサービスとは、グループ企業内の共通業務を一か所に集約する方法です。
シェアードサービスでは、標準化できるルーティン業務の効率化が可能です。ただし、企業間で異なる業務フローの内容や、専門性が高い業務には向かない可能性があります。
一方、従来の部門では、各企業や部署が独自に業務を運営します。たとえば、A社とB社が同じグループ内にある場合でも、各社のやり方で経理処理・人事業務などをおこないます。
シェアードサービスとアウトソーシングの違い
アウトソーシングは、特定の業務を外部企業に委託することを意味します。シェアードサービスでは業務遂行者はグループ内の従業員ですが、アウトソーシングでは社外の担当者が業務を遂行します。
アウトソーシングでは、リソースと併せて社外のノウハウを活用できる点が特徴です。たとえば、給与計算を専門のアウトソーシング企業に依頼することで、最新の法規制に準拠した給与計算や福利厚生や手当の最適化についての相談ができるなど、高い品質のサービスを受けられる可能性があります。
シェアードサービスとBPOの違い
BPO(Business Process Outsourcing:ビジネス・プロセス・アウトソーシング)もアウトソーシングの一種です。したがって、シェアードサービスでは業務をグループ内で実施するのに対し、BPOでは業務を外部に委託します。
プロセスが決まっている業務の一部ではなく、業務プロセスごと委託するアウトソーシングを、特にBPOといいます。そのため、業務プロセス全体の最適化を期待できるのが、シェアードサービスと類似している点です。
シェアードサービスとBPaaSとの違い
BPaaS(Business Process as a Service/ビーパス)とは、特定の業務プロセスをクラウド上で外部企業へアウトソーシングするサービスです。BPO(業務委託)+SaaS(クラウドアプリ)の融合型、といえばイメージしやすいでしょう。
シェアードサービスとの違いはBPOと同様です。ただし、BPaaSでは業務運用だけでなく、クラウドサービスの運用も含まれます。アウトソーシングのなかでも、SaaSやITツールを活用して業務効率化を図り、業務プロセスごと委託するのが特徴です。
なぜシェアードサービスが再注目されているのか

シェアードサービスは、1980年代のアメリカで誕生し、企業の間接業務を集約・効率化する手法として発展してきました。日本では2000年ごろから大企業を中心に導入が進み、近年再び注目を集めています。
昨今の少子高齢化での人材不足や働き方改革の推進により、企業は限られたリソースで業務を効率化する必要に迫られています。これがシェアードサービスが再び注目されている理由のひとつです。
世界のシェアードサービス市場は、今後数年間で飛躍的な成長が予想されています。2023年の9,000万ドルから、2028年には年平均成長率23.3%で2億6,000万ドルに達する見込みです。
日本国内では、2022年度のシェアードサービス市場は前年度比1.6%増の5,670億円との調査結果があります。再注目されている状況と世界市場の急成長を踏まえると、日本のシェアードサービス市場も今後拡大していくと考えられます。
出典:シェアードサービスセンターの市場規模、2028年に2億6000万米ドル到達見込み|CNET Japan
出典:人事・総務関連業務アウトソーシング市場に関する調査を実施(2024年)|株式会社矢野経済研究所
シェアードサービスの組織形態

シェアードサービスの組織形態は、主に2種類あります。「本社の一部門として設立する方法」と「子会社を設立する方法」です。それぞれの概要を見てみましょう。
本社の一部門として設立
1つ目の組織形態は、シェアードサービスを本社の一部門として設立する方法です。既存組織のなかに新たにシェアードサービス部門を作り、業務を集約します。
既存の組織のなかで運営できるため、比較的スムーズに導入しやすい点がメリットです。社員の混乱も少なく、本社の意思決定に基づいて業務改善を進められるため必要に応じて業務範囲を調整しやすいことも特徴です。
一方、本社の影響を受けやすいため、シェアードサービスとしての独立性は低くなります。
子会社を設立
2つ目の組織形態は、シェアードサービスを専用の子会社として独立させる方法です。本社から独立するため、シェアードサービスセンターとしての専門性を高めやすいことが特徴です。
また、グループ内の共通業務(経理、人事、給与計算、ITサポートなど)を集約し、業務の標準化と効率化を実現できます。加えて、グループ全体の業務プロセスを統一することで、内部統制の強化にもつながります。データ管理やセキュリティ対策を一元化することで、リスク管理を強化できるのもメリットです。
一方で、新たに法人を設立するため、初期費用が発生するデメリットがあります。また、大規模な組織変更を要することから、本社の一部門として設立するよりも導入に時間がかかる傾向があります。
シェアードサービスの対象業務

シェアードサービスの対象業務の代表例は、以下のとおりです。グループ間の各企業で内容が共通する業務は、シェアードサービスで集約できます。
- 人事・総務
- 財務・経理
- 情報システム
- 物流
- 法務・監査
人事・総務
シェアードサービスで集約される業務のなかでも、人事や総務は代表的な例のひとつです。入退社手続きや給与計算、福利厚生の管理など、多くの企業で共通する業務が対象となります。
たとえば、従業員の入退社にともなう手続きは、多くの企業で似たような流れをたどります。入退社手続きの一連の業務を統一したルールで処理することで、業務の効率化が実現します。
財務・経理
財務・経理は、法令や規定に沿って処理するため、シェアードサービスとの相性が良い分野です。一般会計や決算業務、債権・債務管理、税務申告など、多くの企業で共通する処理を一元化することで、業務の正確性と効率を高められます。
たとえば、グループ全体の支払い管理を統合すれば、各社でバラバラに処理していた請求業務を一本化できます。作業時間を大幅に削減できるでしょう。また、グループ全体で同じシステムに統一すれば、データの一貫性が保たれ、不正やミスを防ぎやすくなります。
情報システム
システムの運用やヘルプデスク業務など、情報システムの分野もシェアードサービスで集約できる領域です。たとえば、各企業のヘルプデスクを集約し、問い合わせを同一窓口で受け付けることで品質の向上が期待できます。
物流
物流部門においても、シェアードサービスの活用は進んでいます。商品調達や在庫管理、輸送手配などは、企業ごとに大きな差が出にくい業務です。
たとえば、各企業が個別に契約していた配送業者を一本化します。一社ずつ発注をおこなうよりも、割安で依頼できる可能性があります。また、在庫情報を統合すれば、過剰在庫や品切れのリスクを抑えながら、効率的に運用しやすくなるでしょう。
法務・監査
契約書の管理やコンプライアンスチェックなど、法務・監査に関する業務もシェアードサービスの対象です。企業ごとに異なるフォーマットを統一して契約管理を一元化すれば、業務の属人化を防げます。
また、監査業務を集中管理することで不正が起こりにくくなり、内部統制も強化できます。
シェアードサービスのメリット

シェアードサービスのメリットは以下のとおりです。
- リソースの最適化
- ガバナンスの強化
- 業務品質の向上
- 人件費・管理費の削減
リソースの最適化
業務を集約することで、グループ内での業務の重複を減らし、リソースを最適化できます。
たとえば、複数の子会社がそれぞれ独自に経理部門を持っているとします。同じ業務がグループ内の複数の場所でおこなわれることになり効率的ではありません。シェアードサービスを導入すれば、ひとつのセンターで業務を一元化できるため、無駄のない人員配置を実現できます。
ガバナンスの強化
業務を一元管理することで、ガバナンスの強化も可能です。従来の部門運営では、企業や部署ごとに異なるルールが適用されることが多く、内部統制が煩雑になりがちです。
シェアードサービスを導入すれば、統一されたルールのもとで業務が処理されるようになり、透明性のある管理体制が整います。監査の際の対応もスムーズになるでしょう。
業務品質の向上
シェアードサービスを導入することで業務の標準化が進み、品質の向上が期待できます。個別の部門ごとに業務をおこなっていると、異なるルールや担当者のスキルなどによってスピードや品質に差が生じることがあります。
シェアードサービスセンターで統一された管理体制のもとで業務をおこなえば、安定した品質を維持しやすいでしょう。グループ企業同士でナレッジや業務改善のアイデアも共有できます。
人件費・管理費の削減
業務の集約により、人件費や管理費を削減できることもメリットです。各企業が独自の管理部門を持つ場合、人件費やシステム運用費が個別にかかります。
シェアードサービスを導入すれば、必要な人員や設備を最小限に抑えられてコストカットにつながります。
また、ITインフラの統合により、システムのメンテナンス費用も削減可能です。従来は各企業が独自のサーバーやソフトウェアを管理していた場合、シェアードサービスにより共有システムに切り替えることで、サーバーやソフトウェアの維持を企業ごとにする必要がなくなります。また、ソフトウェアの一括契約もできるため、運用やライセンスなどのコストを抑えられるでしょう。
シェアードサービスのデメリット

シェアードサービスのデメリットは以下のとおりです。
- 実施のハードルが高い
- イレギュラーな対応ができないケースがある
実施のハードルが高い
シェアードサービスを導入する際、まず問題となるのが実施の難しさです。特にグループ規模が大きいほど、各企業の業務フローや利用しているシステムに相違が出やすくなります。
また、統合用システムの構築や業務プロセスの標準化に多大な初期投資が必要となり、導入にも時間がかかります。短期的な成果が見えにくいため、スモールスタートで段階的に実施することがポイントです。
まずは特定の業務から始め、成功事例を少しずつ積み重ねていくことで、徐々にシェアードサービスの対象範囲を広げましょう。
イレギュラーな対応ができないケースがある
シェアードサービスを導入すると、特定の業務を専門とする従業員との連携が取りにくくなるケースがあります。特に子会社を設立する場合、突発的なトラブルや専門知識が必要なシーンで、従来よりも対応に時間を要する可能性があります。
たとえば、以下業務でのケースが該当します。
財務・経理部門では、国際会計基準(IFRS)や日本の会計基準に則った財務諸表の作成、税務申告など、深い専門知識が必要です。加えて、各企業の個別の経理処理や業界特有のルールを考慮しなければなりません。しかし、シェアードサービスでは、このような特殊な会計処理が必要な場合に追加確認や調整が発生し、結果的に作業の遅れにつながる可能性があります。
また、税務調査が急に入った場合、現場の経理担当者は調査官からの質問に即座に対応しなければなりません。しかし、シェアードサービスに業務が移管されていると、必要なデータや処理内容を確認するため対応に時間を要する可能性があります。
専門性を持った従業員とすぐに連携が取れなくなると、イレギュラー発生時の対応が難しくなるため、専門的な業務をシェアードサービスの対象外としたり、専任の専門チームを設けたりすることが有効です。
シェアードサービス導入に関する課題と対策
シェアードサービス導入に関する課題として、各グループ企業の業務プロセスが異なるため、業務の標準化が難しいことが挙げられます。特に専門性の高い業務はマニュアル化が難しく、シェアードサービスに適さないケースもあるかもしれません。
シェアードサービスの対応範囲が適切に設定されていないと、各部門のリソースだけが削減される一方で、業務自体はそのまま残ることがあります。人件費や運用コストも依然として高いままで、期待されるコスト削減効果が得られない可能性があります。
この課題を解決するためには、シェアードサービスの導入を段階的に進めることが重要です。まずは標準化しやすい共通業務から集約し、運用を安定させたうえで、対象範囲を広げていくことで、より効果的なコスト削減と業務効率化が実現できます。
シェアードサービスを導入する流れ

シェアードサービスを導入する流れは以下のとおりです。シェアードサービスセンターを設立する場合の流れを5つのステップで紹介します。
- 業務の現状を正しく把握する
- 対象となる業務・部署を洗い出す
- 業務プロセスの標準化・システムを見直す
- シェアードサービスセンターを設立する
- 全社展開し定着化を図る
1. 業務の現状を正しく把握する
まずは、現在の業務がどのように運営されているかを正確に把握しましょう。
- すべての業務プロセスをリストアップ
- 業務の内容や手順を詳細に記録
- 担当者やリソースの配分の把握
- 使用しているシステム、処理フローを整理
上記の情報について従業員へのヒアリングやアンケートを活用して収集します。各部門や拠点ごとにどのような業務がおこなわれているのかを洗い出していきます。
2. 対象となる業務・部署を洗い出す
現場の業務の全体像を把握したら、シェアードサービスに適している業務と、対象となる部署を特定します。一般的に、シェアードサービスに向いているのは以下のような業務です。
- 人事・総務
- 財務・経理
- 情報システム・ITサポート
- 物流
- 法務・監査
一方で、マーケティング戦略や商品開発など、各企業の独自性が強い業務は標準化が難しいため、シェアードサービスの対象外となります。
3. 業務プロセスの標準化・システムを見直す
抽出された課題をもとに、業務プロセスを標準化します。共通のルールや手順を設けて、業務の効率と一貫性を高めましょう。
また、集約後の業務を効率よく遂行するために、システムの見直しもおこないます。各社で共通のシステムを導入することで、シェアードサービスの対象業務を遂行しやすくなります。
4. シェアードサービスセンターを設立する
共通化する業務を一元管理する組織「シェアードサービスセンター」を設立し、業務の運営体制を整えます。シェアードサービスセンターの設立にあたり、以下のような内容を検討しましょう。
- 業務分担
- 役割分担
- オペレーションモデル
- サービスレベルの定義
なお、すべての業務を一度に移行するのではなく、まずは一部の業務や部署で試験運用をおこなうことをおすすめします。試験運用で問題点を洗い出してから本格導入すると効果的です。
5. 全社展開し定着化を図る
試験運用で得られた結果から、システムや運用体制の有効性、課題などを確認します。フィードバックをもとに、課題に対する改善策を講じたうえで全社への導入を進めましょう。
同時に、従業員への教育・研修、コミュニケーション施策をおこない、シェアードサービスの定着化を図ります。
シェアードサービスの成功事例

労働力不足が深刻化するなか、多くの企業が効率的に業務を運営する必要に迫られています。シェアードサービスは間接業務を集約し、少人数での管理を可能にする手法として注目されています。
ここでは、シェアードサービスを実際に取り入れている企業の事例を紹介します。
- 株式会社ダスキン
- 大和ハウス工業株式会社
株式会社ダスキン
クリーンサービス事業などを手掛ける株式会社ダスキンでは、基本方針に基づくテーマのひとつとして「経営基盤の構築」を設定していました。その施策として、シェアードサービスセンターの運用・効率化を推進した実績があります。
過去には、ダスキンおよび連結子会社では、経理・人事業務などで重複した業務を抱えており、管理コストが膨らんでいました。
そこで、2019年にシェアードサービスセンターを設置しました。「ダスキンおよび子会社の経営効率向上への貢献」をミッションとして掲げ、業務の効率化やコスト削減に取り組んでいます。
シェアードサービスセンターの運用・効率化には業務デジタル化が必須であることから、「SmartDB」を導入し、システム基盤を整えました。
デジタル化および本格利用により、30%以上の生産性向上が見込まれています。
参照:ダスキン、会計業務のフロントシステムとして「SmartDB」の本格利用を開始
大和ハウス工業株式会社
大和ハウス工業株式会社は、1955年創業の住宅総合メーカーです。各事業所の負担軽減や企業成長の維持を目的に、分散されていた経理業務を集約してシェアードサービスを実現させました。
同社は、以前にRPAの導入を試みましたが、ITスキルの習得が難しく1年後に撤退しています。その後、業務担当者自らが開発できるノーコード開発基盤である「SmartDB」を採用しました。
「SmartDB」の導入により、人事部の複雑な業務にも対応でき、業務担当者が自ら開発できる点が評価されました。
支払通知書や残高確認書など、各事業所が個別に抱えていた業務負荷を軽減できました。ヒューマンエラーの防止にもつながり、支払い通知までのリードタイムの短縮を実現しています。
大和ハウス工業では人事部門の担当者が主体となり、通常業務と並行しながら導入後3ヵ月で10業務、1年後の2021年12月時点では13業務をデジタル化しました。これにより、複雑なプロセスが発生する解職申請をはじめ、総合福祉団体定期保険に関する意思確認や問い合わせ対応などの業務効率化を実現しました。
大和ハウス工業株式会社様ご講演|視聴申し込み
参照:DXに立ち向かう大企業の先進事例|豪華企業6社出演!【デジタルの民主化DAY Special開催レポート】
シェアードサービスと「SmartDB」の連携による業務デジタル化の推進
シェアードサービスで業務を統合する際、プロセスや使用しているシステムの違いから、標準化に難航することは多いです。また、部署ごとに管理されているデータの横断や、権限管理なども考慮しなければなりません。スムーズな導入を進めるために、共通のシステムを導入することを検討するのもひとつの手段です。
「SmartDB」は、ノーコードで業務デジタル化を実現するプラットフォームです。大企業向けに設計されており、複雑なワークフローにも柔軟に対応できます。
企業ごとにプロセスの異なる業務も、迅速かつ柔軟に統合・標準化します。部署や事業ごとにデータ項目の違いがある場合でも、「SmartDB」はそれらを踏まえたうえで項目の出し分けができる機能を有しています。シェアードサービスの導入効果を最大限に引き出したい方は、ぜひご検討ください。
資料ダウンロードはこちらから
まとめ
本記事では、シェアードサービスについて解説しました。シェアードサービスの導入により、リソースの最適化やガバナンスの強化、業務品質の向上などが期待できます。しかし一方で、シェアードサービスは実施のハードルが高くなりやすいことも特徴です。
シェアードサービスを導入するなら、「SmartDB」を活用することをおすすめします。
「SmartDB」は、ワークフローとWebデータベース機能を備えたノーコード開発プラットフォームです。シェアードサービスを実施している企業でも導入されており、フロントシステムとしてさまざまな業務を効率化できます。
財務会計や人事管理、債務・債権管理など、シェアードサービスの対象業務を一元管理したい企業に最適です。入社申請や各種マスタ情報の管理も可能で、スムーズなデジタル化に役立ちます。
「SmartDB」には以下のような特徴があります。
- 業務に合わせたマスタデータの活用
- 組織横断で利用できる統合データベース
- ERPシステムへの連携まで自動化するワークフロー
「シェアードサービスに必要なツールをスムーズに導入したい」「シェアードサービスで市民開発を実現している成功事例が知りたい」という場合には、ぜひご相談ください。

3分でわかる「SmartDB」
大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」で、どのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。
詳細・お申し込みはこちら